英語を習い始めの時、文の順番は「主語:S」「次に動詞:V」「そして目的語:O」と習いました。
しかしながら、古英語ではSVOだけでなく、SOVの語順が普通に見られたし、OSVやVSOなどの語順もありえました。
現代の観点からは、語順が定まっていない英語など英語ではないかのように感じられるかもしれないですが、SVOの語順の原則ですら、英語の歴史の過程で定着し、規則化してきた代物なのです。
英語の語順の推移を考える前に、まず一般に言語における語順についてみていきましょう。主語(S)、目的語(O)、動詞(V)という3要素の組み合わせに限定して考えると、論理的には、SOV,SVO,OSV,OVS,VSO,VOSの6種類の組み合わせが考えられます。このうち、やはり主題である主語(S)を先頭に持ってくるSOVやSVOが世界の言語を見渡してもトップ2に入ります。SOV(48%)でSVO(32%)です。日本語に照らして考えてみると、「私はバナナを食べる」 (SOV) が自然ですが,「バナナを私は食べる」 (OSV) や「食べる,私はバナナを」 (VSO) なども,不自然さはあるにせよ,文法的に間違いとは言い切れません.でも英語の場合、I eat a banana. が標準的であり,*Eat I a banana. や *A banana I eat. は通常許容されません。
この違いは何でしょう?それは日本語の格助詞のおかげです。「~は」で主語、「~を」で目的語であることが示されているので、順番を入れ替えても意味が通じます。
ところが英語の場合はこのような役割に相当するものがなく、単語を並べるしかないので、「主語」⇒「動詞」⇒「目的語」といった基本的な語順を決めて、語順をみればどれが主語か、目的語かがわかるようにしたのです。
ちなみに、英語とルーツを同じくするドイツ語については、名詞に「格」がつきます。父を意味するVaterにderという格がつくと、der Vaterで「父は」という主語になります。dem Vaterで「父に」、den Vaterで「父を」という目的格になります。名詞の格を見れば、主語か、目的語かわかるような仕組みになっています。
実は、古い英語にはドイツ語のように格があったのですが、時代を経ていく中で、使われなくなり、代わりに語順で主語、動詞、目的語がわかるようにしたのです。次の文章は古い英語の語順の一例です。
S-V型 Hit rinde.「雨が降った」(it rained)
V-S型 Rinde hit.(rained it)
S-V-O型 He hæfde anne godne sunu.「彼はよい息子をもった」(he had a good son)
S-O-V型 He anne godne sunu hæfde. (he a good son had)
このような多くの型は昔は多く見られましたが、語形で区別がつかなくなってくると、やはり主語のあとに目的語が来るよりも、動詞が来る方がしっくりきますし、何よりも相手の関心をひきつけるに、主語を先頭にもってくるのが自然です(日本語でも、基本的には誰が~どうするという語順ですね)。そういうことで、英語は14世紀頃までにS-V型に統一されていきました。
同じ名詞の主語と目的語の混乱を避けるうえで、主語を動詞の前に置くという原則を確立することは極めて有効な解決策だったのですね~。
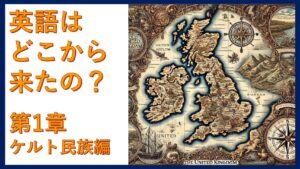
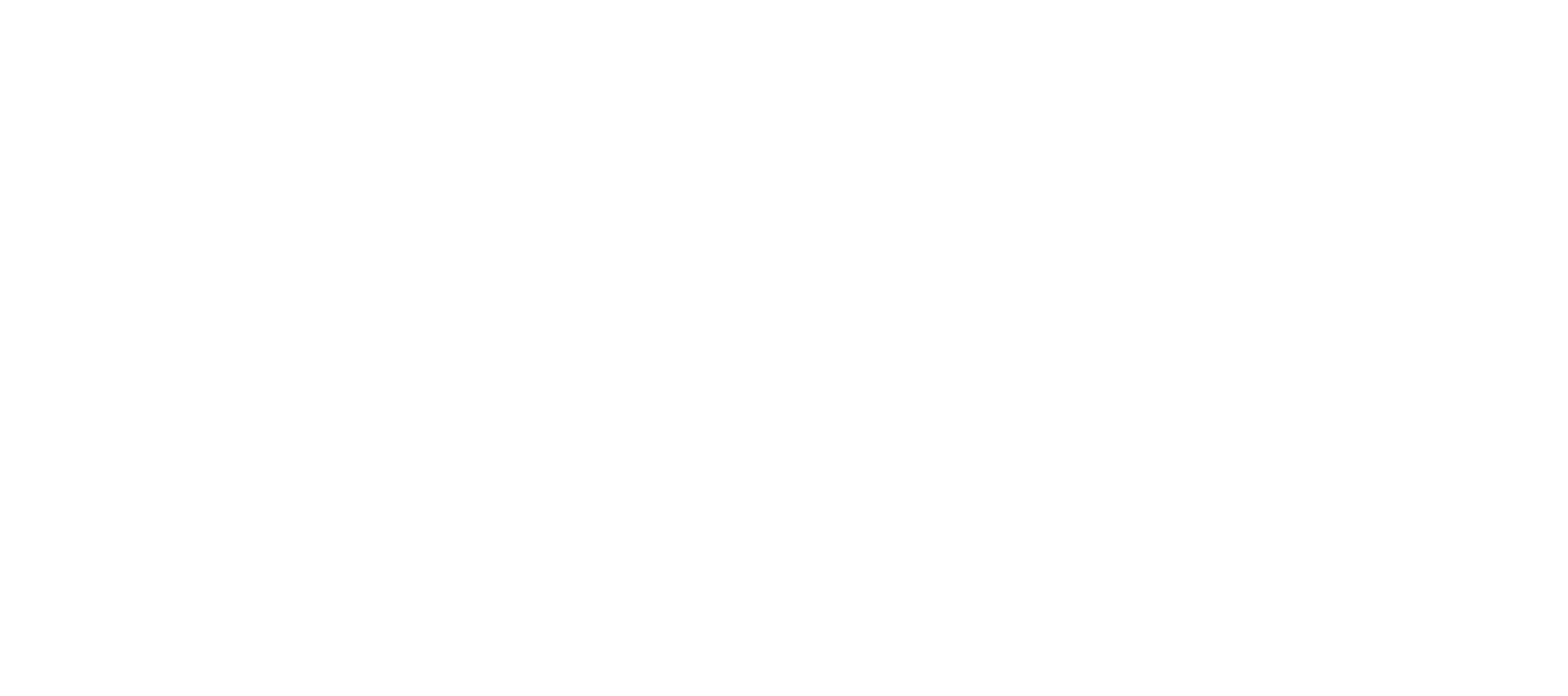
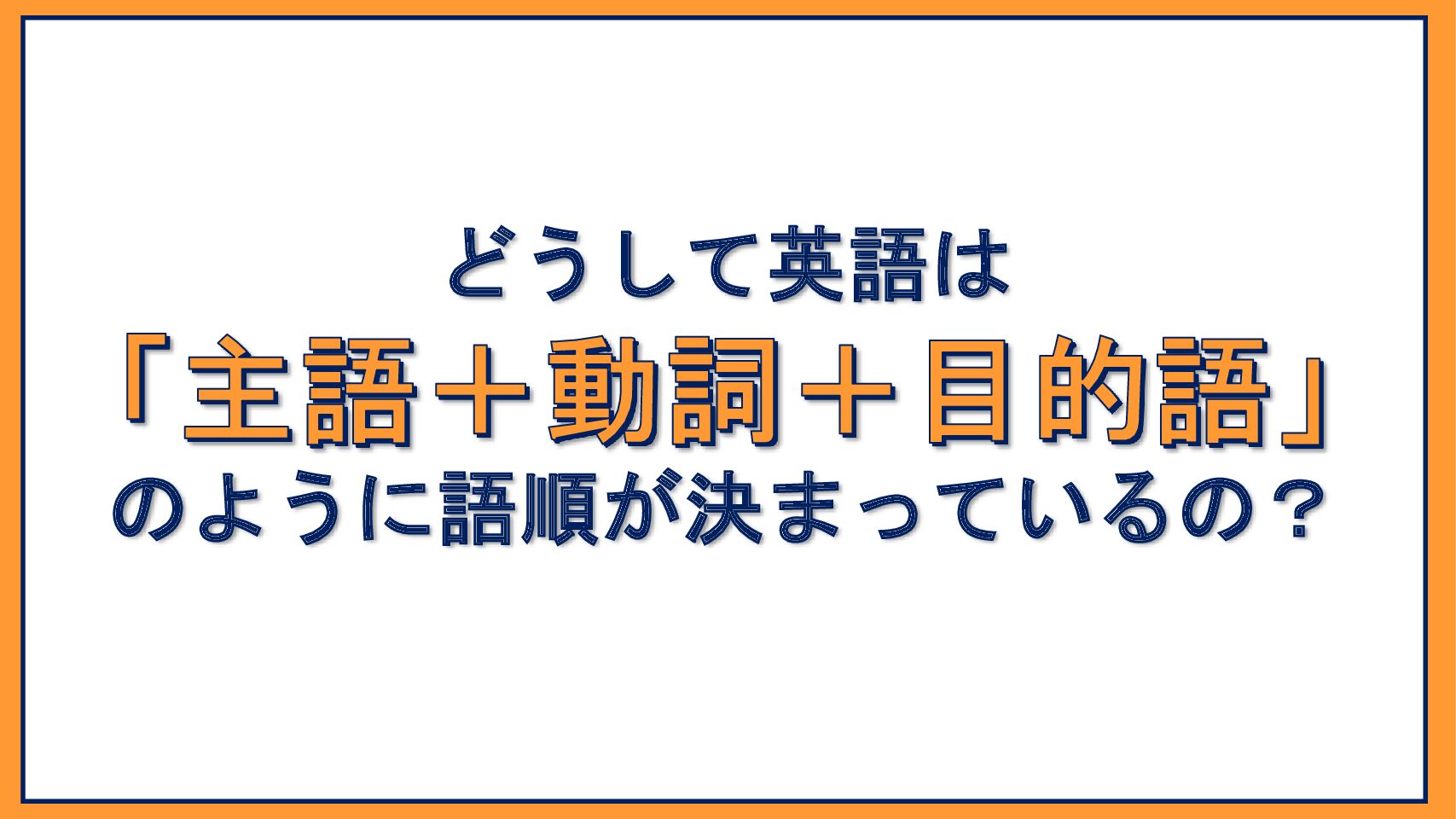

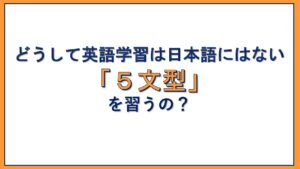
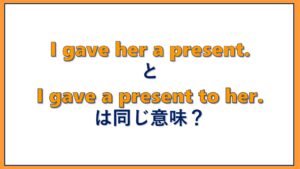
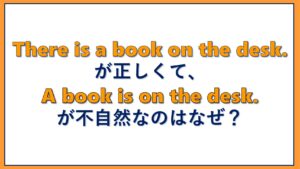
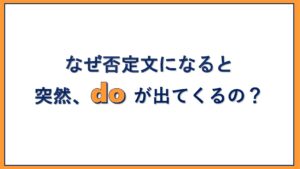
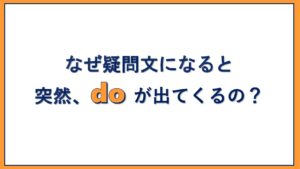
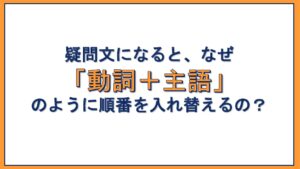
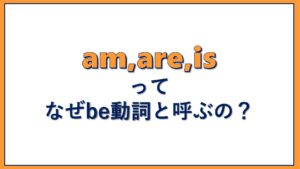
コメント