前回の記事「なぜ、疑問文になると突然、doが出てくるの?」に関連しては今度は、否定文についてdoが登場する理由について勉強していきます。
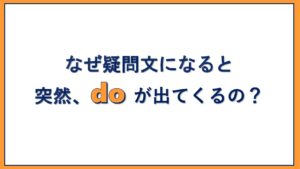
You are smart.を否定文にすると、You are not smart.のように主語とbe動詞の間にnotを入れて否定文を作ります。
ところが、You speak English.のように、一般動詞がくると、否定文は
You speak not English.ではなくYou do not speak English.となり、突如としてdoが出てきます。これは何故でしょうか?”I don’t say”を例に否定文の歴史を振り返ってみましょう。
①11世紀頃 Ic ne secgne.(I say not.)
②14世紀 I ne seye not.
③15世紀 I say not.
④16世紀 I not say.
⑤17世紀 I do not say.
⑥18世紀 I don’t say.
否定文にdoが現れたのは、16世紀以降とされています。古英語の時代では否定辞neが動詞の前に置かれる①のような形式が、否定文の代表的な構造だったようですが、この形式は徐々にnothingの意味を持つnohtを文末に付加することで”強化”されるようになり、nohtはnotとなって中英語期の典型的な形式②が生じました。その後、意味的にも音声的にも存在価値の小さくなったneは脱落することが多くなり、1400年ごろには③の形が普通の形になります。その後、16世紀以降にdoが少しづつ使用されはじめて、17世紀には⑤の形が一般的な否定文になったと言われています。そして、最後の段階として、notが縮約されてdoに後接された⑥が生じました。意外にも現代の英語と同じ用法が確立したのは、最近なのですね~。
ちなみに英語と同じゲルマン語族に属する、ドイツ語では、否定の意味を表すnichtが文末に残る③に近い形が現代でも使われています。
例)「今日は泳ぎません」
英語:I do not swim today.
ドイツ語:Ich schwimme heute nicht.
英語は話している途中で、否定かどうかが分かりますが、ドイツ語は最後まで聞かないと否定かどうかが分からないのです。その点、日本語と同じですね。
さて、どうして英語だけ途中で、doが登場して、さらに動詞の前にnotが付くのでしょうか?しかもこのdoには「行う」の意味はありません。何かあえて登場させる意味があったのでしょうか?これについては、前回の記事「なぜ、疑問文になると突然、doが出てくるの?」で示したように、使役の意味でも使われていたdoの意味が弱まって、もはや意味をなさない単なる「記号」になったのではないか?という説が1つ。「主語+動詞」の語順を好む英語の性格からして、④I not say.から⑤I do not say.への変化は、「主語のあとに動詞が欲しい」という英語の欲求を満足させる変化であったという説もあります。
このように、言語と言うのはある1つの理由からではなく、語順という規範意識に即した理由だったり、諸々相互作用しながら、成熟していったといえるでしょう。
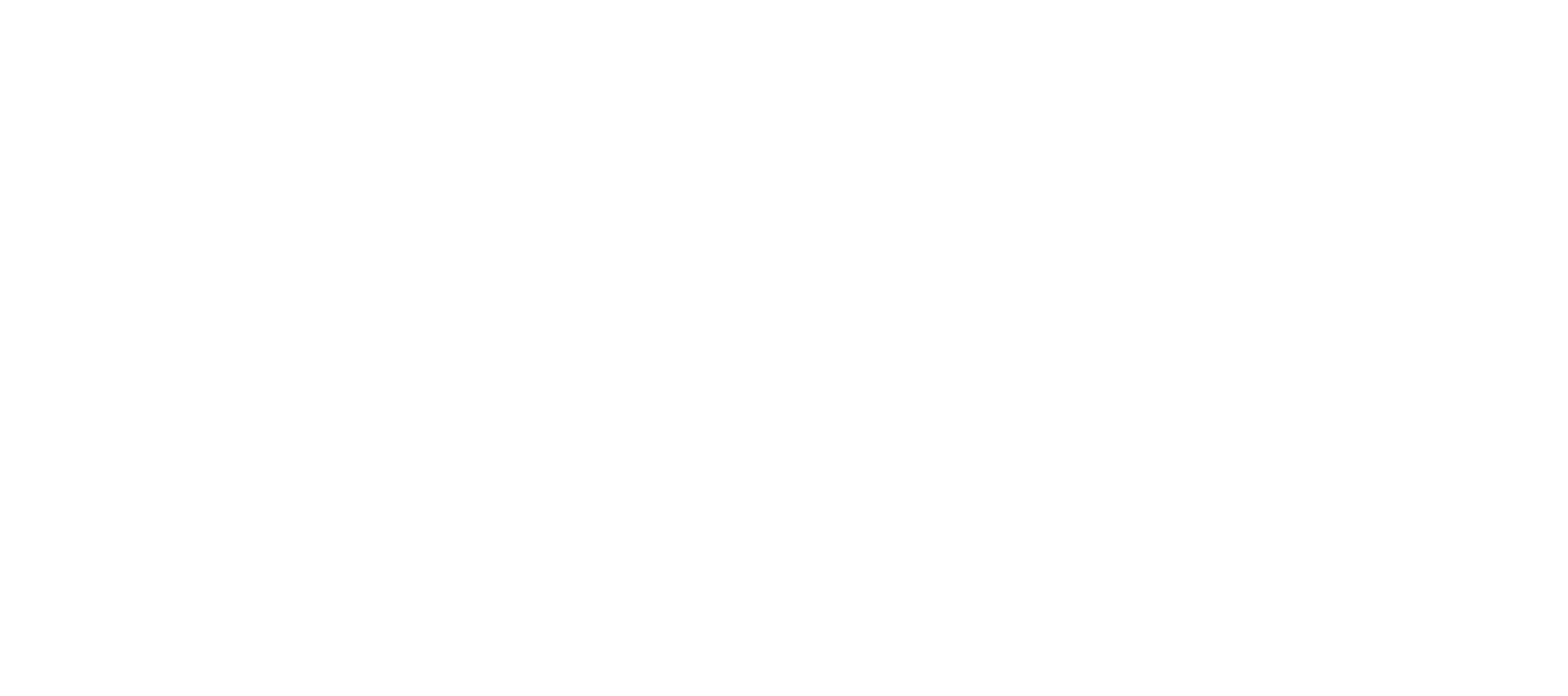
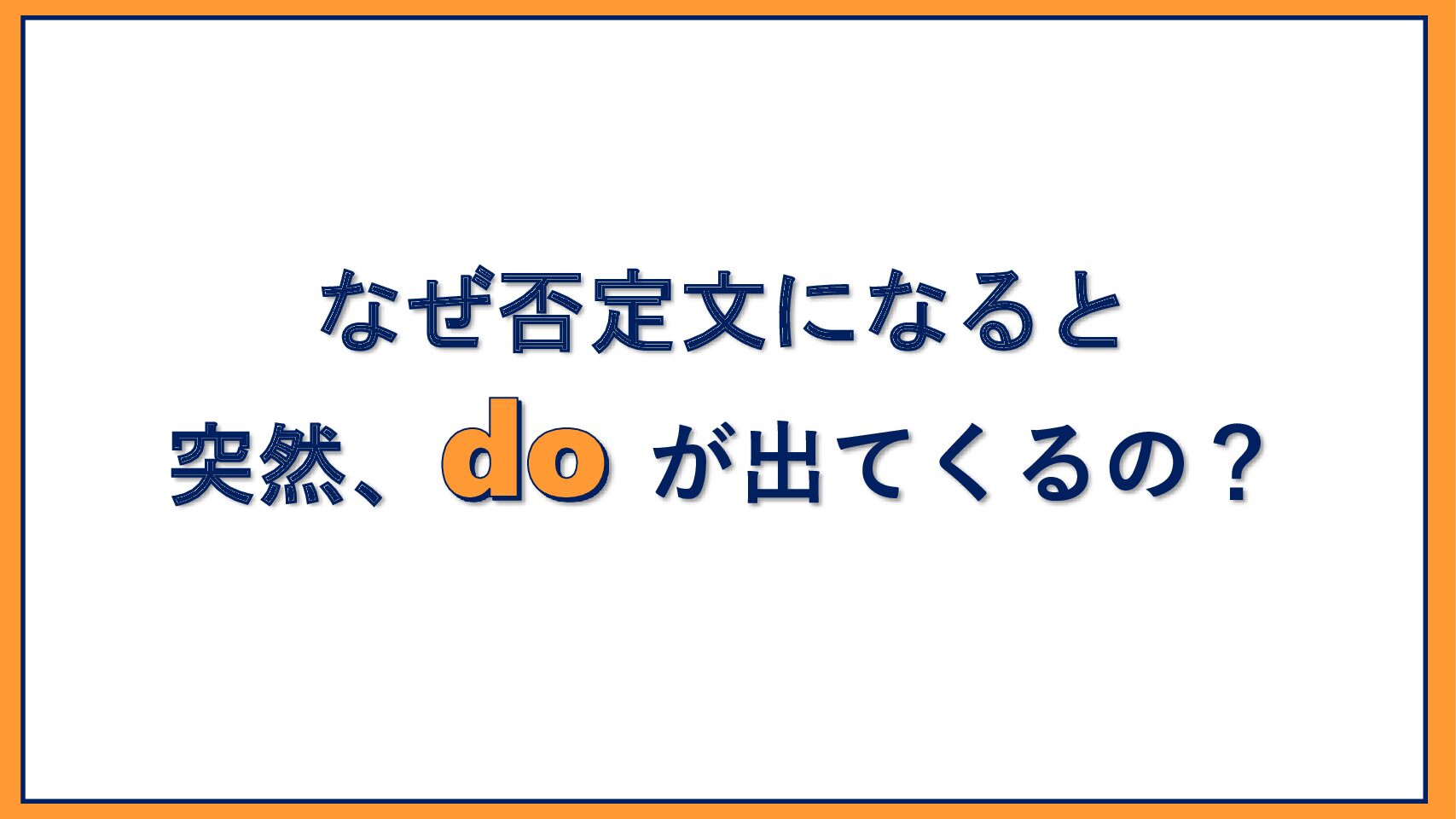

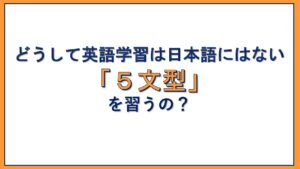
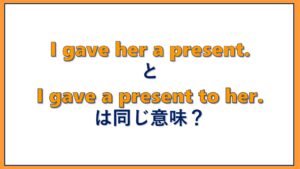
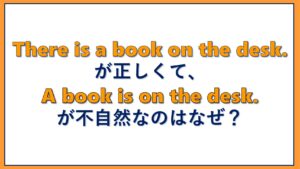
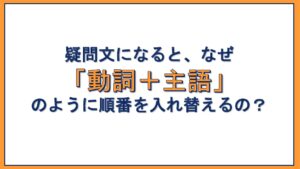
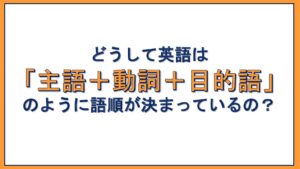
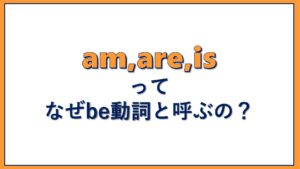
コメント